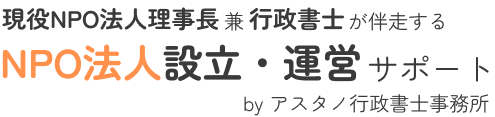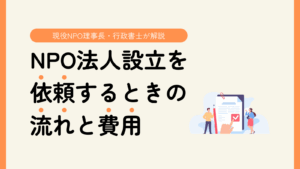NPO法人は自分で設立する?専門家に依頼する?|メリット・注意点、比較と判断のヒント
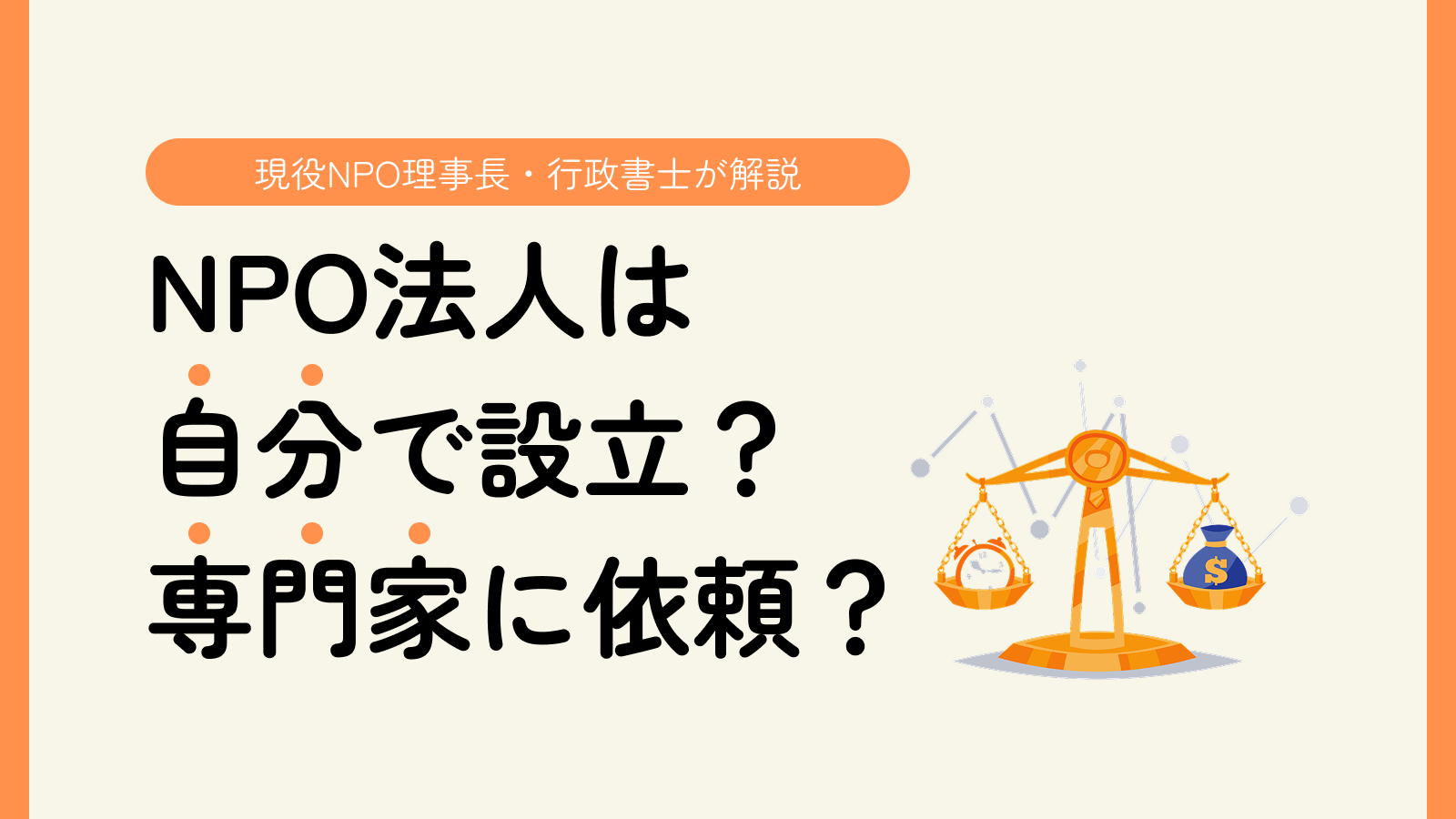
- NPO法人を作りたいけれど、手続きがむずかしそうで不安…
- 自分でやるか、専門家に頼むか、どっちがいいのかわからない
- ネットの情報が多すぎて、何が正しいのか判断できない
実際、NPO法人の設立は「自分でできる」と言われる一方で、ミスや手戻りが多いのも事実。
費用だけでなく、時間や労力のかかり方もまったく違います。
この記事では、「自分で設立する場合」と「専門家に依頼する場合」の違いを、メリット・注意点や判断のヒントを交えて、わかりやすく解説します。
この記事を読むことで、自分に合った方法が見えてくるので、設立の第一歩に自信を持って進められるようになります。
迷ったときは、無理にひとりで抱え込まず、無料相談などをうまく活用して判断するのが安心です。
NPO法人は自分でも設立できる!手続きの全体像とポイント解説
NPO法人は、専門家に頼まなくても、時間と労力をかければ自分で設立することができます。
実際に多くの人やボランティア団体が、自分たちで設立の手続きを完了させています。
手続きの全体像としては、以下の通りです。
- 基本事項を検討する
- 定款と設立に必要な書類を作成する
- 設立総会を開催し、議事録を作成する
- 所轄庁へ認証申請をする
- 認証後に法務局で登記する
- 税務署・自治体などへ設立届を出す
- 法人名義の口座を開設し、活動をスタートする
- 設立後の運営体制を整える
各ステップの詳しい進め方は、以下の記事で解説しています
上記のような作業を、ネットの情報や支援機関を活用しながら進めていく事例も多くあります。
自分で設立する場合のメリット・注意点
自分でのNPO法人を設立する際には、メリットと注意点の両方を理解しておくことが大切です。
以下に自分で設立する場合のメリット・注意点をまとめました。
| メリット | 注意点 |
|---|---|
| 費用を抑えられる 制度や仕組みへの理解が深まる 自分たちのペースで進められる | 手続きや書類が複雑で時間がかかる 書類不備による差し戻しのリスク 相談先が少なく、孤立しやすい |
メリット①:費用を抑えられる
自分でNPO法人を設立すれば、専門家への依頼費用を節約することができ、全体のコストを大きく抑えられます。
NPO法人の設立では、株式会社などと異なり、登録免許税がかからず、定款の認証手数料も不要です。
さらに、書類作成や住民票などの取得を自分で行えば、最低限の実費だけで設立することも可能です。
以下の表では、「自分でやる場合」と「専門家に依頼する場合」のそれぞれのケースで発生する主な費用項目と、その目安を比較しています。
| 費用項目 | 自分でやる場合 | 専門家に依頼する場合 |
|---|---|---|
| 定款認証手数料 | 0円 | 0円 |
| 登録免許税 | 0円 | 0円 |
| 法人の実印作成 | 5,000円~30,000円 | 5,000円~30,000円 |
| 住民票や印鑑証明書などの取得 | 300円~1,000円/通 | 1,000円~3,000円/通 |
| 専門家への依頼費用 | 0円 | 200,000円~300,000円 |
メリット②:制度や仕組みへの理解が深まる
自分でNPO法人の設立手続きを進めることで、制度や運営の仕組みについて深く理解することができます。
- 制度・運営の仕組みが自然と理解できる
書類作成や申請の流れを通じて、NPO法人がどのように成り立ち、運営されているのかが見えてきます。 - 設立後の運営にも早くから意識が向く
総会の準備や報告書の作成など、設立後に必要な実務も見据えながら進めることができ、スタートがスムーズになります。 - 自団体の方針や仕組みを言語化できる
定款づくりを通して、「自分たちは何を目的に活動するのか」「どうやって意思決定するのか」など、団体の方向性を整理することができます。
メリット③:自分たちのペースで進められる
自分で手続きを進めることで、スケジュールや進め方を柔軟に調整でき、自分たちのペースで設立準備を進められます。
以下のように、スケジュール面や判断の自由度において、大きなメリットがあります。
- 必要に応じて立ち止まり、考える時間がとれる
定款の内容など、納得いくまで話し合って決めたい部分も、自分たちのペースで進められます。 - 忙しい人でも無理なく進められる
本業や家庭との両立をしながら、自分の空いた時間で準備ができるので、負担が少なくて済みます。
注意点①:手続きや書類が複雑で時間がかかる
自力でNPO法人を設立することは可能ですが、以下のような負担やリスクにも注意が必要です。
- 書類の数が多くて複雑
申請には10種類以上の書類が必要になることも。定款、設立趣旨書、事業計画書など、1つずつ丁寧に準備する必要があります。 - 書き方やルールに厳密さが求められる
書式や記載内容にミスがあると、所轄庁から差し戻され、再提出になるケースもあります。 - 手続きに時間がかかる
自分で進める場合、調べながら準備するため、書類作成に何日もかかることがあります。
注意点②:書類不備による差し戻しのリスク
自分で設立手続きを進める際に注意すべきなのが、「細かなミス」による差し戻しです。
特に以下のようなポイントは、実務でもよくある見落としなので注意が必要です。
- 定款と役員構成が一致していない
たとえば定款では「理事3名」と記載しているのに、提出書類では2名しかいないなどのズレがあると、差し戻されることがあります。 - 活動目的や内容が曖昧
所轄庁は「誰に・何を・どう届けるのか」が明確でないと、活動実態がないと判断し、認証されないことがあります。 - 署名や押印が漏れている
設立総会議事録や委任状など、印鑑や署名が必要な書類の押し忘れが原因で、再提出になるケースも少なくありません。
注意点③:相談先が少なく、行き詰まりやすい
自力で設立を進めるうえで、意外と多くの人がつまずくのが「相談先がない」という点です。
特に初めての方にとっては、判断に迷う場面で不安を抱えがちです。
- 提出書類に自信が持てない
所轄庁は形式チェックが中心で、内容のアドバイスまではしてくれないケースが多いです。 - ネット情報がバラバラで判断しにくい
記事によって内容が違ったり、自分の地域では通用しなかったりすることもあります。 - 手順や進め方で迷ったときに行き詰まる
「どの順番で進めればいい?」「ここで止まっていいの?」といった不安に、自力で答えを出すのが難しいことがあります。
実際に自分で設立を進める場合は、あらかじめ手続きの流れを理解しておくことが重要です。
各ステップの具体的な進め方については、以下の記事でくわしく解説しています
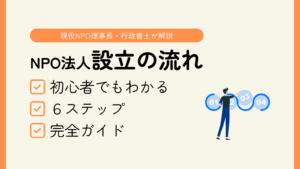
専門家に依頼する場合のメリット・注意点
以下に専門家に依頼する場合のメリット・注意点をまとめました。
| メリット | 注意点 |
|---|---|
| スムーズかつ確実に設立できる 制度に詳しく、対応に強い 書類のクオリティが高い | 費用がかかる 内容を把握しないまま設立してしまうリスク サポート内容によっては実情に合わない書類になる |
メリット①:スムーズかつ確実に設立できる
専門家に依頼すれば、設立手続きをスムーズかつ確実に設立を進めることができます。
書類作成や申請手続きに精通しているため、無駄な時間やミスを減らし、確実に所轄庁へ申請を通すことが可能です。
- 書類の準備に迷わない
必要な書類や記載方法を専門家が案内してくれるので、調べる手間が大幅に減ります。 - 自治体ごとのルールにも対応できる
所轄庁ごとの細かい運用や審査傾向を把握しているため、的確な申請が可能です。 - 差し戻しのリスクが低い
書式ミスや記載漏れなどを事前に防げるため、スムーズに設立を進められます。
メリット②:制度に詳しく、対応に強い
専門家に依頼することで、制度変更や所轄庁の運用ルールに柔軟に対応した書類作成・申請が可能になります。
自治体ごとの審査傾向や細かなルールを把握しているため、「どこに注意すべきか」を事前に見越した対応ができます。
- 法改正や提出様式の変更にもすぐに対応
NPO法やガイドラインが変わっても、最新情報を踏まえた申請が可能です。 - 自治体ごとの独自ルールにも精通
「この様式は◯◯市だけ必要」「この文言は避けたほうがいい」など、現場の対応力があります。 - 事前相談・調整もスムーズ
不安な点は所轄庁と事前に調整し、通りやすい申請になるよう支援してくれることもあります。
メリット③:書類のクオリティが高い
専門家に依頼することで、審査に通りやすく、第三者にも伝わりやすい高品質な書類を作成できます。
所轄庁や助成金審査などの目線を意識した文面や構成により、単なる形式だけでなく「中身の伝わる書類」に仕上がります。
- 活動目的や内容が明確に伝わる
専門家のアドバイスをもとに、言葉を整理し、分かりやすく具体的な表現に整えられます。 - 審査側の視点を踏まえて作成される
「この書き方だと通りやすい」といった実務のノウハウが活かされ、差し戻しのリスクを減らせます。 - 設立後にも使える書類になる
定款や事業計画書は、助成金申請・外部説明にも使われるため、汎用性の高い仕上がりになります。
注意点①:費用がかかる
専門家に依頼する場合、自力で設立する場合に比べて一定の費用が発生します。
手続きの内容やサポート範囲によって金額は異なりますが、設立コスト全体に大きな差が出ることもあります。
以下の表では、「自分でやる場合」と「専門家に依頼する場合」のそれぞれのケースで発生する主な費用項目と、その目安を比較しています。
| 費用項目 | 自分でやる場合 | 専門家に依頼する場合 |
|---|---|---|
| 定款認証手数料 | 0円 | 0円 |
| 登録免許税 | 0円 | 0円 |
| 法人の実印作成 | 5,000円~30,000円 | 5,000円~30,000円 |
| 住民票や印鑑証明書などの取得 | 300円~1,000円/通 | 1,000円~3,000円/通 |
| 専門家への依頼費用 | 0円 | 200,000円~300,000円 |
注意点②:内容を把握しないまま設立してしまうリスク
専門家にすべてを任せる形で手続きを進めると、制度の仕組みや団体のルールを十分に理解しないまま、設立が完了してしまうケースがあります。
これは、設立後の運営トラブルや、助成金申請時のつまずきにつながることもあります。
- 定款や事業計画の中身を理解していない
形としては完成していても、「何が書かれているのか分からないまま提出した」というケースは少なくありません。 - 制度上の義務や運営のルールを知らない
社員総会の開催義務や所轄庁への報告義務など、設立後の流れを把握しないままスタートしてしまう危険性があります。 - 代表者や役員の意識に差が生まれる
「自分は何の責任を持っているのか?」を理解しないまま名前だけ載っているという状況が、後々の衝突や不安につながることも。
注意点③:サポート内容によっては実情に合わない書類になる
サポート内容や進め方によっては、団体の実情や方針がきちんと反映されていない定款や書類が作成されてしまうことがあります。
これは、設立後の運営や助成金申請の際に「使いづらい書類」になってしまう原因になります。
- 活動内容が抽象的すぎる
テンプレートに沿って作成された結果、「自分たちの活動に合っていない文言」がそのまま残ってしまうことがあります。 - 運営実態に合わないルールが定款に書かれている
実際は毎月理事会を開いているのに、定款には「年1回」と記載されているなど、運営と齟齬が生じるケースがあります。 - 助成金や連携先に説明しにくくなる
設立後、定款や事業計画書を見せる機会は多く、内容がずれていると「実態が見えにくい団体」と思われる恐れがあります。
専門家に依頼する場合の具体的な流れや費用の目安については、以下の記事でくわしく解説しています。(※準備中)
自分でやる vs 専門家に依頼|違いを比較表でチェック
「自分で設立する場合」と「専門家に依頼する場合」、それぞれにメリット・注意点があることはお伝えしてきました。
ここでは、それらの違いを一目で把握できるように、比較表にまとめました。
| 項目 | 自分でやる場合 | 専門家に依頼する場合 |
|---|---|---|
| 費用 | 実費のみ(1万〜3万円程度) | 依頼費用が追加(20万〜30万円程度) |
| 所要時間 | 自分で調べる時間が必要/数週間〜数ヶ月 | 最短2〜3週間でスムーズに進行 |
| 難易度 | 書類作成や制度の理解が必要 | 書類作成や申請は任せられる |
| 柔軟性 | 自分のペースで進められる | 専門家とのやり取りが必要 |
| 書類のクオリティ | 書き方に不安が残ることも | 通りやすく、後から使いやすい内容に仕上がる |
| リスク | 差し戻し/申請ミスの可能性あり | 制度対応やミス防止のノウハウあり |
NPO法人の設立はどちらが向いている?判断のヒントまとめ
「自分でやるべきか?それとも専門家に依頼すべきか?」迷ったときは、まずはそれぞれの特徴を整理してみましょう。
以下の表では、費用や時間、安心感などの観点から違いを比較しています。
| 比較ポイント | 自分でやるのが向いている人 | 専門家に頼むのが向いている人 |
|---|---|---|
| 費用 | 費用を抑えたい | 費用より安心感を優先したい |
| 時間 | 時間にゆとりがある | 短期間で設立したい |
| 関心度 | 自分で制度を学びたい | 手続きは任せて本業に集中したい |
| ミスの不安 | 自分で調べながら進められる | ミスや差し戻しを避けたい |
| 書類の質 | 最低限通ればOK | 外部への説明や助成金でも使いたい |
こんな人は自分で設立するのもアリ!
「時間に余裕がある」「費用を抑えたい」「制度に興味がある」といった方は、自力での設立にも十分チャレンジできます。
- 費用をできるだけ抑えたい
設立時の出費を最小限にしたい方は、自分で進めることで依頼費用を省くことができます。 - 時間に余裕がある
調べながら書類を作成したり、所轄庁に確認したりする時間を確保できる方は、自力でもスムーズに進められます。 - 制度を理解しながら進めたい
書類の構成やルールを自分で把握しておくことで、設立後の運営にも役立てたい方にはおすすめです。
こんな人は専門家に依頼した方が安心!
「なるべく早く設立したい」「ミスが不安」「自分でやる自信がない」そんな方には、専門家への依頼がおすすめです。
- 短期間で確実に設立したい
必要書類を揃えて、ミスなくスピーディーに進めたい方にとっては、専門家の力が大きな支えになります。 - 制度や書類に不安がある
ルールが複雑で不安、調べるのが大変…という方には、正確なアドバイスと代行が安心につながります。 - 助成金や連携を見据えて“伝わる書類”を整えたい
設立書類をその後も活用したい方にとって、クオリティの高い書類を作ってもらえるのは大きなメリットです。
まとめ|迷ったときは、無料相談を活用しよう
この記事では、「自分でNPO法人を設立する方法」と「専門家に依頼する方法」の違いや、それぞれのメリット・注意点について解説しました。
要点をまとめると以下の通りです。
- 自分で設立する場合は、費用が抑えられ、制度への理解も深まるが、ミスや手間がかかりやすい
- 専門家に依頼すれば、書類のクオリティや通過率が高く、スムーズに設立できるが、一定の費用が発生する
- ご自身の状況や目的に応じて、比較表や判断のヒントをもとに選ぶことが大切
NPO法人設立では、「費用」「時間」「安心感」のバランスをどう考えるかが重要なポイントとなります。
どちらを選ぶにしても、ご自身の優先順位を明確にしたうえで、後悔のない選択をすることが大切です。
NPO法人設立を自力で進める場合の流れは、以下の記事で解説しています
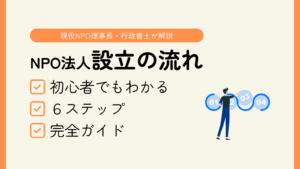
専門家に依頼したい場合の流れや費用は以下の記事で解説しています※準備中
「まだ迷っている…」「直接相談したい」という方は、お気軽にご相談ください。