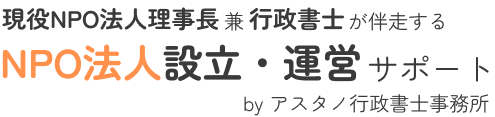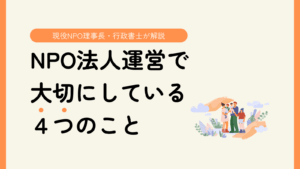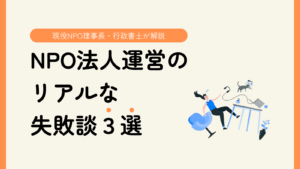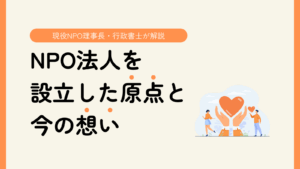初めての助成金申請|採択された私が伝えたい3つの書き方のコツ
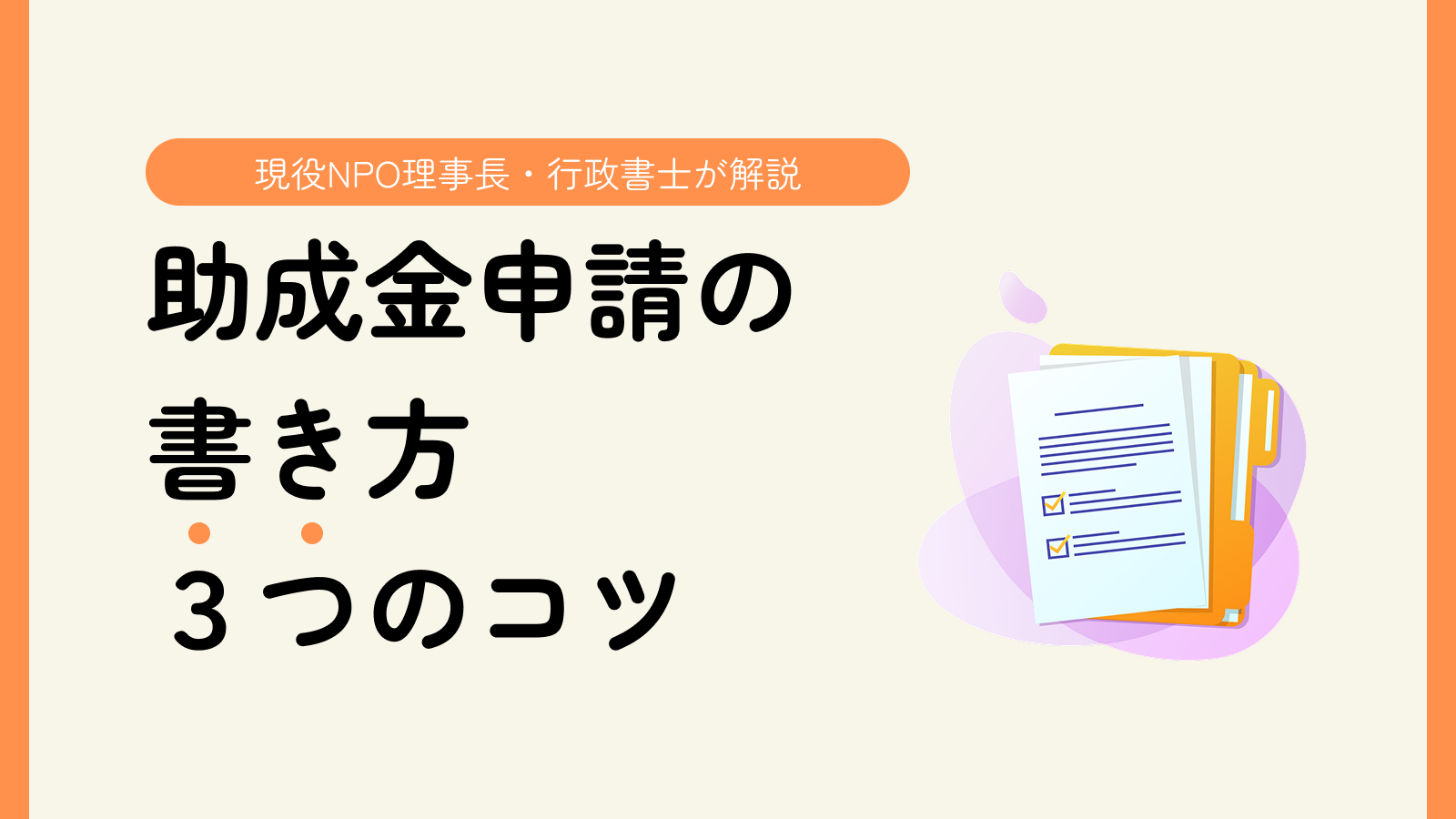
- 助成金に挑戦したいけれど、申請書の書き方がわからない
- 公募要領を読んでも、何をどう書けばいいのかイメージできない
- 頑張って書いても、本当にこれで伝わるのか不安になる
助成金申請は、特別なスキルが必要なわけではありません。
「伝え方のポイント」を押さえるだけで、初めての方でも採択を目指すことは十分に可能です。
この記事では、筆者自身の初申請の実体験をもとに、申請書で意識すべき3つのポイントを、初心者向けにやさしく解説しています。
この記事を読むことで、初めて助成金に挑戦するNPO法人の方が、申請書で押さえるべきポイントを具体的に理解し、採択につながる書き方のコツを身につけられます。
大切なのは、伝えたい想いを「読み手に伝わる形」に変えること。
そして一人で悩まず、必要な場面で支援を受けながら、一歩を踏み出すことです。
初めての助成金申請。正直、迷いもありました
初めて助成金を申請したのは、大学3年生のときでした。
助成金の申請には、事業の目的や計画、予算の根拠などを詳しく記載した申請書を作成する必要があります。
当時の私は、その書き方がまったく分からず、とても戸惑ったのを今でもよく覚えています。
さらに、大学の授業とアルバイトで毎日が忙しく、申請書の作成に十分な時間を確保するのが難しい状況でした。
「せっかく一生懸命作っても、不採択になったらどうしよう…」と不安になり、申請そのものを諦めようかと悩んだことも何度もありました。
それでも一歩踏み出して申請してみたことで、大きな学びと自信につながりました。
申請書で意識した3つのポイント
1.助成金の公募(案内)要領を読み込む
助成金には必ず 「公募要領(案内文)」 と呼ばれる資料が付いています。
これは助成金の趣旨・目的、申請条件、採択のポイントなどがまとめられた重要なガイドラインです。
多くの方は 助成金の金額 にまず目が行きがちですが、それ以上に大切なのは 「その助成金が目指す社会をどう実現したいのか」 という視点です。
申請書を書く際も、この 趣旨・目的 に沿った形で、一貫性のある内容にまとめることがとても重要です。
公募要領の「趣旨・目的」の項目には、助成金を提供する側の 背景や意図 が詰まっています。
ここを読み飛ばしてしまうと、申請書の方向性がずれてしまうことも。
まずは丁寧に公募要領に目を通し、提供側がどんな想いでこの助成金を設けているのかを理解することからスタートしてみてくださいね。
2.申請書は一貫性+5W1Hでまとめる
助成金の申請書は、つい「あれもこれも」と盛り込みたくなり、内容が支離滅裂になりがちです。
そんなときこそ内容を絞り、一貫性を意識してまとめることが大切です。
その際に役立つのが、5W1H(いつ・どこで・誰が(に)・何を・なぜ・どのように)という考え方です。
この順番を意識して書くと、読みやすく整理された申請書になります。
- いつ → 今年8月下旬に
- どこで → 大阪市内の○○公民館で
- 誰に → 経済的に恵まれない子どもたちに
- 何を → 学習支援を行う
- なぜ → 貧困層や経済格差の影響で学校外教育を受ける機会が減っているから
- どのように → 地元の大学生に協力してもらい、子どもたちに無償で支援を行う
このように シンプルで明確なストーリー にまとめることで、審査員にも活動の内容や意義が伝わりやすくなります。
3.現実的な範囲内で記載する
審査員は、申請者の活動の規模や内容だけでなく、「この計画は本当に実現可能か」「持続可能か」 という観点でも申請書を判断しています。
今の活動規模を大幅に超える内容や、常識からかけ離れた予算計画は現実味がないと見なされ、不採択につながりやすい傾向があります。
そのため、「今できること+少し成長した姿」 をイメージした計画がベストです。
「無理のない範囲で、着実に実現できる内容」 を意識して記載しましょう。
背伸びしすぎず、今後の成長も見据えた誠実な計画こそが、審査員の信頼を得やすくなります。
採択されたときに感じたこと
私が初めて採択された助成金は、中辻創智社の「困難な状況にある子ども達への学習支援」 でした。
「私たちの活動が初めて認められた」 と感じた瞬間は、今でも心に強く残っています。
同じNPO法人の役員だった学友たちと力を合わせて申請書を作り上げた努力が報われ、心から嬉しい気持ちでいっぱいでした。
また、この経験が「もっと活動を頑張ろう!」「今度はこんなことを実現したい」 という前向きな気持ちを生み出し、次のチャレンジへの大きなモチベーションになりました。
今後申請する人へのアドバイス
まずは何よりも、公募(案内)要領をしっかり読み込むことが本当に大切です。
活動計画がどんなに素晴らしくても、経費の計画や申請内容が公募要領に沿っていなければ 不採択になるケースが少なくありません。
たとえば、公募要領に 「人件費は最大5万円まで」 と記載されているのに、申請書に 「人件費10万円」 と書いてしまうと、それだけで失格になってしまいます。
こうした 基本的な確認不足による不採択 は本当に残念なことです。
だからこそ、申請書作成前に 公募要領の内容をしっかり理解する ことが欠かせません。
ただし、助成金によっては公募要領が 何十ページにも及ぶ ことも少なくありません。
お仕事や日々の活動で忙しい中、そこに十分な時間を確保するのは簡単なことではないと思います。
そんなときは、一人で抱え込む必要はありません。
私たち NPO法人専門のアスタノ行政書士事務所 が、助成金申請書作成のサポートを行い、皆さまに寄り添って伴走いたします。
一歩踏み出したい方は、どうぞお気軽にご相談ください。
一緒に形にしていきましょう。
まとめ|“伝える力”が支援につながる
今回の記事では、助成金申請書の書き方や注意点についてお伝えしてきました。
要点をまとめると、以下の通りです。
- 公募要領をしっかり読み込むことが、採択への第一歩となる
- 申請書は5W1Hを意識し、一貫性のある内容にまとめることが大切
- 実現可能性や継続性を意識した、無理のない計画を書くことが重要
助成金申請では、「活動への想い」を読み手に伝わる形に整理して届けることが重要なポイントとなります。
NPO法人の皆さまにおかれましては、ぜひこのポイントを押さえて、採択につながる申請書づくりに取り組んでみてください。
そして、一人で抱え込まず、迷ったら誰かに相談することも大切です。
どんな些細なご質問でも構いません。
私たちアスタノ行政書士事務所も、皆さまの活動を少しでも後押しできるよう、全力でサポートいたします。