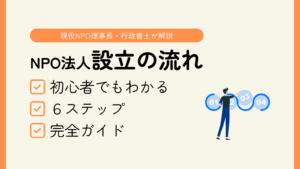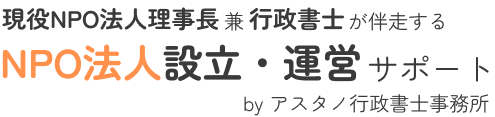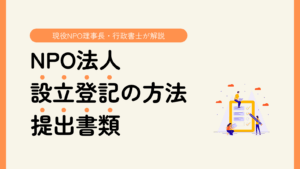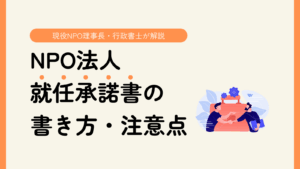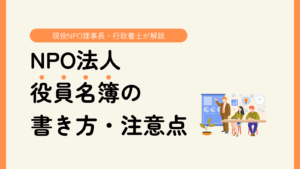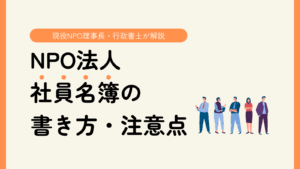NPO法人の設立書類と定款の書き方|雛形&チェックリストでミス防止!
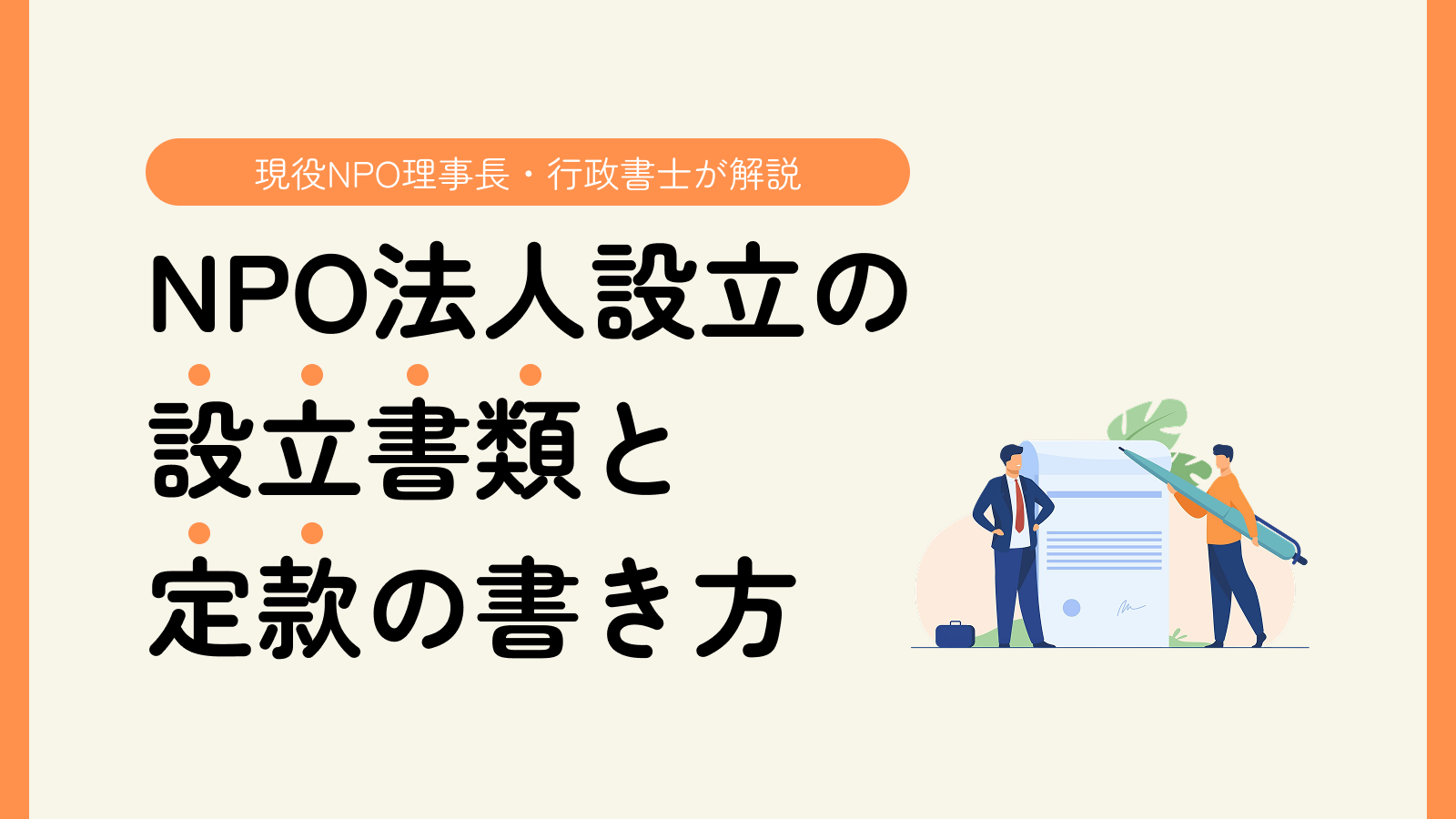
- NPO法人の設立に必要な書類が多すぎて、何から準備すればいいかわからない
- 定款って難しそう…どこまで細かく書けばいいの?
- 書類に不備があって差し戻されたらどうしようと不安になる
NPO法人を設立するには、正確な書類と明確な定款の作成が欠かせません。
しかし、はじめての方にとってはそのハードルが高く、ネットで調べても断片的な情報ばかりで混乱しがちです。
この記事では、NPO法人設立に必要な書類と定款の基本構成・書き方を、雛形とチェックリストつきでやさしく解説しています。
この記事を読めば、NPO法人設立に必要な書類と定款の作成ポイントがひと目でわかり、スムーズに準備を進めることができます。
複雑に見えるNPO法人設立の手続きも、安心して一歩ずつ進められるようになります。
NPO法人に必要な書類一覧【チェックリストつき】
NPO法人の設立には、所轄庁に提出するための書類を揃える必要があります。
ここでは、初心者でも迷わず準備できるように、必要な書類を一覧表で整理しました。
| 書類名 | 概要 |
|---|---|
| 設立認証申請書 | 設立認証を申請するための書類で、法人名・代表者・所在地などの基本情報を記載する |
| 定款 | 団体の目的・組織体制・運営方法など、基本的なルールを定めた書類 |
| 役員名簿 | 役員全員の氏名・住所・役職・報酬の有無を一覧で記載する |
| 各役員の就任承諾及び誓約書のコピー | 各役員が就任に承諾し、法令遵守などを誓約する旨を記載した書類 |
| 各役員の住所又は居所を証する書面 | 各役員の住民票の写し(原本)を提出する |
| 社員名簿 | 設立時の社員(正会員)10人以上の氏名・住所を記載する名簿 |
| 確認書面 | 団体が政治団体や暴力団などに該当しないことを確認する書類 |
| 設立趣旨書 | 団体を設立する背景や目的を説明する書類で、社会的意義を示す |
| 設立総会の議事録のコピー | 設立総会での議決内容や出席者を記録した議事録(署名・押印が必要) |
| 事業計画書(設立初年度及び翌年度) | 初年度および翌年度に行う事業の内容や実施時期を記載する |
| 活動予算書(設立初年度及び翌年度) | 初年度および翌年度の収入・支出の見込みを記載した予算書 |
上記書類の1つでも不備があると差し戻しになります。
特に「定款」「設立趣旨書」は、審査でよく見られるポイントなので、ていねいに準備しましょう。
定款はNPO法人の“ルールブック”|登記や認証に不可欠
定款(ていかん)は、NPO法人のルールをまとめた大事な書類です。
設立するときには、所轄庁に申請したり、登記したりするときにも必要です。
「誰がどう決める?」「お金はどう使う?」など、ルールを決めておかないと、後でトラブルになることもあります。
定款には以下のようなことを記載します。
- 活動の目的や内容(どんなことをする団体なのか)
- 会員や役員の決め方(誰が参加できて、どんな役割があるのか)
- 総会や議事録のルール(いつ、どんなふうに話し合いをするのか)
- お金の使い方(どこに、どのように使うか)
- 合併や解散のルール(団体を終わらせるとき、どのようにするか) など
定款の書き方と条文の解説
第1章 総則
第1条 名称【必須】
第1条 この法人は、特定非営利活動法人○○○○という。
この条文では、NPO法人の正式な名称を決めます。
定款に記載する名称には、「特定非営利活動法人」という言葉を必ず含めなければなりません。
「○○○○」には、NPO法人の正式な名称を記載する
同名法人が存在しないか事前確認しておくと安心
第2条 事務所【必須】
第2条 この法人は、主たる事務所を○○○○内に置く。
2 この法人は、前項のほか、その他の事務所を○○○○内、…に置く。
この条文では、法人の主たる事務所の所在地(本拠地)と、必要に応じてその他の事務所(支所・活動拠点など)を記載します。
「○○○○」には、「市区長村名」まで記載する(番地やビル名は不要)
その他の事務所は、現時点で予定がある場合のみ記載(なければ削除可)
所轄庁の管轄もこの条文で決まるため、「本拠地の市区町村」は慎重に選ぶ
第2章 目的及び事業
第3条 目的【必須】
第3条 この法人は、○○○○に対して、△△△△に関する事業を行い、××××に寄与することを目的とする。
この条文では、団体の活動目的を明確にします。
「誰に対して」「どんな事業を通じて」「何に貢献するのか」を簡潔に一文で表します。
「○○○○」=支援対象(例:子ども、高齢者、外国人など)
「△△△△」=具体的な取り組み内容(例:学習支援、食事提供、相談事業など)
「××××」=最終的な社会的ゴール(例:地域福祉の向上など)を記載する
第4条 特定非営利活動の種類【必須】
第4条 この法人は、その目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第2条別表のうち、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)○○○○
(2)△△△△
(3)××××
この条文では、団体が行う活動が「NPO法で定める20種類の活動分野のうち、どれに当てはまるか」を明記します。
これは、所轄庁の認証において最もチェックされる部分の一つです。
NPO法で定める20種類の活動分野
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
NPO法で定める20種類の活動分野の中から、少なくとも1つ以上、正式な名称で記載する
迷ったときは「目的」と「事業内容」にあっているかを基準に選ぶ
第5条 事業【必須】
第5条 この法人は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動にかかわる事業
① ○○○○事業
② ○○○○事業
(2)その他の事業
① △△△△事業
② △△△△事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、利益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
この条文では、団体が実際に行う「事業の内容」を、特定非営利活動(NPO法に基づく活動)と、それ以外の事業に分けて明記します。
「何をやる団体なのか?」を具体的に説明する部分であり、目的条文と整合性が取れていることが重要です。
1:特定非営利活動にかかわる事業は、第4条で記載した活動分野に関連するものを具体的に記載する
(例:学習支援事業など)
2:その他の事業は、本来の目的とは直接関係しない活動を具体的に記載する。
(例:運営資金の確保を目的とした物販やイベント、寄付付き商品の販売、会員向けの相互扶助的な事業など)
※その他の事業を行わない場合、「(2)その他の事業」「2 前項~とする。」は削除可
第3章 会員
第6条 種別【必須】
第6条 この法人の会員は、次の○種とし、正会員をもって法上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
この条文では、NPO法人における会員の区分(種類)とその定義を示します。
また、「法上の社員(=議決権をもつ構成員)」が正会員であることを明記する、非常に重要な条文です。
条文の解説
正会員は、総会の議決権を持つ構成員
賛助会員は、議決権を持たない支援者・協力者
「○種」は、会員の区分が2種類なら「2種」と記載(通常は2種が多い)
第7条 入会【必須】
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
この条文では、団体の会員になるための手続きや条件を定めます。
特に「入会の申込方法」「理事長の承認権限」「入会拒否時の対応」について記載することで、入会希望者とのトラブルを防ぐ目的があります。
条文の解説
会員の入会は、原則として誰でも可能です(=条件は特にありません)
入会希望者は、理事長あてに入会申込書を提出する必要があります
※申込書の様式は団体で自由に決められます(紙でもフォームでもOK)
理事長は、正当な理由がない限り、入会を断ることはできません
入会を認めない場合は、その理由を書面で伝える必要があります
特に変更する必要はありません
第8条 入会金及び会費【必須】
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
この条文では、会員が団体に対して入会金や会費を支払う義務があることを明記します。
具体的な金額や納入方法については定款には書かず、総会で別に決定する(≒柔軟に変更できる)ようになっています。
条文の解説
会員は、入会時や毎年の活動に対して、入会金や会費を納める必要があります
金額は定款には記載せず、社員総会(=正会員の集まり)で別に決めるようにしておきます
→金額を後から変更したい場合でも、定款変更ではなく総会決議で対応できるので実務的です
会費をゼロ円に設定することも可能です(定款の文言はこのままで問題ありません)
特に変更する必要はありません
なお、理事会で決めたい場合は、この条文の「総会」→「理事会」と書き換えることも可能です
第9条 会員の資格の喪失【必須】
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して○年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
この条文では、会員がいつ・どのような理由で会員資格を失うのか(=退会・失格の条件)を定めます。
トラブルを防ぐために、あらかじめ明文化しておくことが非常に重要な条文です。
条文の解説
会員資格は、以下のような場合に自動的に失います
- 本人が退会届を出した場合
- 死亡または所属団体の解散
- 一定期間以上の会費滞納
- 総会の決議などによる除名処分 など
また、除名の具体的な手続きや決議要件については、別条(第11条)で補足しておくと安心です。
「○年」の部分に、団体の方針に応じて「1〜2年」程度の数字を記入してください。
第10条 退会【必須】
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
この条文では、会員が自らの意思で退会する場合の手続きを定めます。
「退会手続きの方法」を明記しておくことで、スムーズな退会とトラブルの回避につながります。
条文の解説
会員は、退会したいときに自由に辞めることができます
退会の際は、理事長あてに「退会届」を提出する必要があります
「退会届の様式」は、団体側で自由に決めることができます(紙・デジタルいずれでもOK)
特に変更する必要はありません。
第11条 除名
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
この条文では、会員の除名(資格喪失)に関する要件・手続き・保障を定めます。
特に「弁明の機会を与えること」が明記されており、恣意的な除名を防ぐための最低限の手続的保障を示しています。
条文の解説
除名は、会員にとって最も重い処分のひとつです
手続きを公正にするため、総会の議決によって行うことが求められます
対象となるのは、以下のようなケースです
- 定款に違反した場合(例:会費未納・運営妨害など)
- 法人の信頼や目的を損なうような行為をした場合
特に重要なのが、「本人に弁明の機会を与える」という点です。
一方的な処分を防ぎ、公平性を保つために、この手続きを省略することはできません。
特に変更する必要はありません
なお、理事会で決めたい場合は、この条文の「総会」→「理事会」と書き換えることも可能です
第4章 役員及び職員
第12条 種別及び定数【必須】
第12条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 3人以上○○人以下
(2)監事 1人以上○○人以下2 理事のうち、1人を理事長、○人を副理事長とする。
この条文では、NPO法人に必ず置かなければならない役員の種類・人数・役職を定めます。
「理事」と「監事」は法律で義務付けられており、設立時にも必ず必要となる項目です。
条文の解説
NPO法人には、最低でも理事3人・監事1人を置く必要があります
この条文では、上限人数も定めておくことで、将来的な組織拡大にも対応しやすくなります。
また、理事のうち1人を理事長(代表者)とし、必要に応じて副理事長を何人か指定することも可能です。
副理事長の人数は任意ですが、定款に明記しておく必要があります。
「○○人以下」の部分には、団体の規模に応じた最大人数を記載します(例:理事10人以下、監事3人以下など)
副理事長を置かない場合は、「○人を副理事長とする」の記載は削除してください
上限人数を定めないケースでは、「3人以上」や「1人以上」のみでも認証されることがありますが、明確にしておく方が望ましいです
第13条 選任等【必須】
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
この条文では、役員の選び方(選任方法)と、親族関係や兼任に関する制限について定めています。
NPO法人の透明性・公正性を確保するために、法令上必要とされるルールが盛り込まれています。
条文の解説
理事・監事は、社員総会(正会員による会議)で選任します
理事長・副理事長は、選ばれた理事の中から理事同士の話し合い(互選)で決定します
特定の家族が役員に偏って就任しすぎないように、親族制限(3親等以内が1人まで、または全体の1/3未満)が設けられています
監事は、理事や職員を兼ねてはいけません(チェック機能を担うため)
特に変更する必要はありません。
なお、副理事長を置かない場合は、「副理事長」の文言を削除してください
第14条 職務【必須】
第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況若しくはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、又は理事会の招集を請求すること。
この条文では、理事長・副理事長・理事・監事それぞれの役割や責任を明記します。
NPO法人としての健全な運営体制を築くため、誰が何を担当するのかを具体的に示すことが重要です。
条文の解説
理事長は法人の代表者かつ最高責任者として、業務を全体的に統括します
理事長以外の理事には代表権はなく、理事会の決議に基づいて業務を行います
副理事長は理事長の補佐役および不在時の代行者として機能します
監事は、理事の業務や法人の財産について監査(チェック)を行う立場です
→ 不正や重大な問題がある場合には、総会・所轄庁への報告権限も持ちます
特に変更する必要はありません。
なお、副理事長を置かない場合は、「副理事長」→「理事」に置き換えてください
第15条 任期等【必須】
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任期満了前に、就任後2事業年度が終了した後の総会において後任の役員が選任された場合には、当該総会が終結するまでを任期とし、又、任期満了後後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
この条文では、役員の任期や、辞任・補欠など特別な場合の扱いについて定めています。
「空白期間をつくらない」「後任が決まるまで責任を持つ」といった考え方を反映した、実務的にも重要な内容です。
条文の解説
役員の任期は原則2年で、再任(何度でも)可能です
後任が選ばれない場合でも、次の総会が終わるまでは現役員が職務を続けることになります
補欠や増員によって途中から就任した場合は、前任者や現任者の残り任期を引き継ぎます
辞任や任期満了後も、次の人が正式に就任するまでは職務を続ける義務があります(引き継ぎがない状態を防ぐため)
特に変更する必要はありません。
なお、任期「2年」は変更可能ですが、1年未満は避けるべき(安定運営に不向き)です。
第16条 欠員補充【必須】
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
この条文では、役員の人数が一定数を下回った場合に、早急に補充しなければならないことを定めています。
法人運営に必要なガバナンス体制を維持するためのルールです。
条文の解説
理事や監事のうち、3分の1を超える人数が欠けた場合には、そのまま放置せず、できるだけ早く補充する必要があります。
特に変更する必要はありません。
第17条 解任【必須】
第17条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
この条文では、役員が重大な問題を起こした場合や適格性を欠いた場合に、総会の議決で解任できるルールを定めます。
また、解任前には必ず弁明の機会(自己弁護のチャンス)を与える必要があることも明記されています。
条文の解説
役員が職務をまっとうできない状態にある場合や、不正・不適切な行動をとった場合には、社員総会の議決により解任することができます
解任は重大な処分にあたるため、本人に事前に弁明の機会を与えることが義務付けられています
特に変更する必要はありません。
第18条 報酬等【必須】
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
この条文では、NPO法人における役員報酬の上限(人数比率)と、費用弁償の可否、報酬等の決定手続きを定めます。
NPO法のルールを守りつつ、実態に応じた報酬設定ができるようにする条文です。
条文の解説
NPO法人では、役員に報酬を支払うことができますが、全体の3分の1以内に限られます
→これは営利目的でない組織であることを明確にするための法律上の制限です
役員が活動にかかった費用(交通費、備品費など)は、必要に応じて弁償(支払い)することが可能です
具体的な報酬額や弁償のルールについては、総会での議決を経て、理事長が定める仕組みとされています
特に変更する必要はありません。
なお、具体的な報酬額や弁償のルールについて、理事会で決めたい場合は、この条文の「総会」→「理事会」と書き換えることも可能です
第19条 職員
第19条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は、理事長が任免する。
この条文では、NPO法人において事務局長やスタッフなどの職員を置くことができること、およびその任命権限が理事長にあることを定めます。
日常的な運営を支えるスタッフに関する基本的なルールです。
条文の解説
この法人では、必要に応じて事務局長や職員を置くことができます(必須ではありません)
職員の採用や退職などの判断は、理事長の権限で行います
特に変更する必要はありません。
第5章 総会
第20条 種別【必須】
第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
この条文では、法人の最高意思決定機関である「総会」には2種類あることを定めています。
定期的に開催される「通常総会」と、必要に応じて開催される「臨時総会」があります。
条文の解説
総会は、法人における最も重要な会議で、役員の選任や予算の承認などを行います
「通常総会」は、毎年1回など定期的に開催される総会です
「臨時総会」は、特別な議題がある場合に必要に応じて開催されます
特に変更する必要はありません。
第21条 構成
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
この条文では、NPO法人における総会の構成メンバーが“正会員(法上の社員)であることを明記します。
正会員が集まって話し合い、法人の重要事項を決定します。
条文の解説
総会は、NPO法人の最高意思決定機関であり、その構成員は「正会員」のみです
賛助会員やボランティアなどは、総会の議決権を持ちません(定款で別途定めない限り)
特に変更する必要はありません。
第22条 権能【必須】
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び活動予算並びにその変更
(5)事業報告及び活動決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第 48 条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項
この条文では、NPO法人の総会で議決すべき事項(=団体として重大な意思決定)を具体的に定めています。
法人運営の中で、特に影響が大きい内容は、正会員の合意を得て進める必要があります。
条文の解説
総会は、NPO法人の意思決定の場として、定款変更・予算承認・役員選任など重要な事項を議決します
借入や合併・解散などの法的・財務的に重大な行為も総会の承認が必要です
「その他重要事項」という項目を含めることで、想定外の議案にも柔軟に対応できます
特に変更する必要はありません。
なお、(4)〜(10)の項目については、理事会で議決することも可能ですが、一般的には総会で決議するのが通例です。
理事会で議決できるようにする場合は、第31条(理事会の権限)との整合性を取る必要があります。
第23条 開催【必須】
第23条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
(3)第14条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
この条文では、通常総会の開催頻度と、臨時総会が開催される具体的な条件を定めています。
法人としての意思決定をいつ・どのように行うかを明確にする、重要な運営ルールです。
条文の解説
「通常総会」は、毎事業年度に1回必ず開催する定例の総会です
「臨時総会」は、必要に応じて開催するもので、以下の場合に行います
- 理事会からの招集請求があった場合
- 正会員の5分の1以上から招集請求があった場合
- 監事から、法人運営に関して重大な問題があると判断された場合
特に変更する必要はありません。
なお、「5分の1以上」という割合は、定款でより厳しい条件に変更することは可能です(例:3分の1以上、4人以上など)。
ただし、5分の1未満(例:10分の1以上など)に緩和することはできません。
第24条 招集【必須】
第24条 総会は、第23条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、第23条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から 15 日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。
この条文では、総会を誰が・どのようなタイミングで・どうやって招集するかを定めています。
スムーズで公平な意思決定を行うための重要なルールです。
条文の解説
総会は原則として理事長が招集しますが、監事が招集する場合(第23条第2項第3号)は例外です
理事会や正会員から臨時総会の請求があった場合、理事長は15日以内に開催しなければなりません
招集通知は、少なくとも5日前までに、開催日時・場所・目的・議題を明記して、書面またはメール等(電磁的方法)で送る必要があります
特に変更する必要はありません。
第25条 議長
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
この条文では、総会の議長(進行役)を誰が務めるかについて定めています。
議長は、総会を円滑かつ公正に進行させるために必要な役割です。
条文の解説
議長は、その場に出席している正会員の中から選出します
特に変更する必要はありません。
第26条 客足数【必須】
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
この条文では、総会を開催するために必要な最低出席者数(=定足数)を定めます。
ルールの整った意思決定を行うための、重要な要件です。
条文の解説
総会を開催するには、正会員全体の2分の1以上の出席が必要です
特に変更する必要はありません。
第27条 議決【必須】
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
この条文では、総会で何を議決できるか・どのような方法で決議が成立するかを定めています。
意思決定のルールを明確にすることで、公平で透明な運営が可能になります。
条文の解説
総会では、事前に通知された議題のみを議決の対象とします(急な追加議題による混乱を防ぐため)
原則として、出席した正会員の過半数の賛成で可決されます
賛否同数の場合は、議長が最終判断を行います
また、全員が書面や電子的に同意した場合には、実際に総会を開かずとも決議があったものとみなすことができます(いわゆる「みなし決議」)
特に変更する必要はありません。
第28条 表決権等【必須】
第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号及び第 49条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
この条文では、正会員の表決権の平等性、出席できない場合の対応、出席の取り扱い、利害関係がある場合の制限について定めています。
正会員による公平かつ適正な意思決定を支えるための基本ルールです。
条文の解説
すべての正会員の表決権は平等であり、1人1票の原則が適用されます
やむを得ず総会に出席できない場合は、書面・電磁的方法による表決や、代理人による委任が可能です
このように表決した正会員は、定足数・議決数の計算上「出席したもの」として扱われます
議題に関して特別な利害関係を持つ正会員は、その議決には参加できません(公正な判断を守るため)
特に変更する必要はありません。
第29条 議事録
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名し、又は記名押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)総会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
この条文では、総会を開催した際に作成すべき「議事録」の内容と署名者のルール、さらにみなし決議があった場合の議事録の扱いについて定めています。
議事録は、団体の運営記録として所轄庁に提出したり、トラブル防止の根拠資料になる重要書類です。
条文の解説
総会の議事録には、日時・出席者数・審議内容・結果などの基本事項を記載する必要があります
また、議長と選任された議事録署名人2名以上の署名または押印が必須です
書面・電磁的同意による“みなし決議”の場合にも、内容・提案者・決議日・記録者などをまとめた議事録を作成しなければなりません
特に変更する必要はありません。
第6章 理事会
第30条 構成
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
この条文では、理事会を構成するメンバーは理事であることを明確に定めています。
理事会は、法人の運営に関する重要な意思決定を行うための機関です。
条文の解説
理事会は、理事のみで構成される会議体であり、監事や正会員は含まれません
特に変更する必要はありません。
第31条 権能【必須】
第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
この条文では、理事会がどのような事項を議決できるか(=権限の範囲)を定めています。
総会が“団体全体の意思決定機関”であるのに対し、理事会は主に“日常の運営や実行を担う機関”です。
条文の解説
理事会は、主に日常的な運営や執行に関する事項を議決します。具体的には以下の通りです。
- 総会にかけるべき議題の事前決定
- 総会で可決された内容の実施に関する手続き
- その他、総会の承認を要しない日常的な会務の実行に関すること
特に変更する必要はありません。
第32条 権能
第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき
(3)第14条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
この条文では、理事会がどのような条件で開催されるかを定めています。
理事会が恣意的に開かれすぎたり、逆に開かれなかったりしないよう、客観的な基準を設けるための条文です。
条文の解説
理事会は、次のような場合に開催されます
- 理事長が必要と判断したとき
- 理事の3分の1以上から、目的事項を記載した書面や電磁的方法(メール等)で招集請求があったとき
- 監事から招集請求があったとき(例:業務・財産に重大な問題があると判断された場合)
特に変更する必要はありません。
第33条 招集
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、第32条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。
この条文では、理事会を誰が・どのようなタイミングで・どうやって招集するかを定めています。
スムーズな開催と公正な進行のために必要なルールです。
条文の解説
理事会は、原則として理事長が招集します。
理事または監事から招集請求があった場合は、理事長はその日から15日以内に理事会を開く必要があります。
招集通知は、会議の5日前までに送るのが原則です。通知には、日時・場所・目的・審議事項を明記し、書面またはメール等(電磁的方法)で行います。
特に変更する必要はありません。
第34条 議長
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
この条文では、理事会における議長(進行役)は理事長が務めることを定めています。
会議の秩序を保ち、意思決定を円滑に進めるための基本ルールです。
条文の解説
理事会の議長は、法人の代表者である理事長が務めるのが原則です
特に変更する必要はありません。
第35条 議決
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
この条文では、理事会で議決できる内容の範囲と、議決のために必要な賛成数(=議決要件)を定めています。
適正な意思決定を保証するための基本ルールです。
条文の解説
理事会では、事前に通知された議題のみを議決の対象とします(サプライズ議題は禁止)
議決には、理事総数の過半数の賛成が必要です(出席者の過半数ではない点に注意)
可否が同数になった場合は、議長(通常は理事長)が最終判断を行います
特に変更する必要はありません。
第36条 表決権等
第 36 条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第37条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
この条文では、理事会における表決の原則・書面や電磁的方法での表決・特別利害関係のある理事の制限について定めています。
適正な意思決定と公正性を保つための基本的なルールです。
条文の解説
理事の表決権はすべて平等(1人1票)です
出席できない理事も、事前通知された議題に限り、書面または電磁的方法(例:メールなど)で表決が可能です
書面や電磁的に表決した理事は、出席者としてカウントされます(第37条の定足数計算に含まれる)
議題に対して特別な利害関係を持つ理事は、その議決には参加できません(利益相反の防止)
特に変更する必要はありません。
第37条 議事録
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名し、又は記名押印しなければならない。
この条文では、理事会の内容を記録するための議事録の作成要件について定めています。
総会と同様、議事録は法的証拠としての役割を持ち、所轄庁や外部監査に提出されることもある重要な記録です。
条文の解説
理事会の議事録には、会議の基本情報・出席状況・審議内容と結果・署名者の選任などを明記する必要があります
書面や電磁的方法で表決した理事がいる場合は、その旨を明確に記録しておくことが求められます
議事録には、議長と、選任された議事録署名人2名以上の署名または押印が必要です
特に変更する必要はありません。
第7章 資産及び会計
第38条 資産の構成【必須】
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立の時の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄附金品
(4)財産から生じる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益
この条文では、NPO法人が保有する資産の内訳(構成要素)を明示しています。
どのような収入源・財産が法人の運営資源となるかを明確にしておくことで、会計処理や資産管理の基準にもなります。
条文の解説
法人の資産は、以下のようなものから構成されます
- 設立時に提出した財産目録に記載された資産
- 正会員・賛助会員などからの入会金や会費
- 一般の支援者や企業などからの寄附金や寄附物品
- 預貯金や不動産などの保有資産から生じる利息・賃料等の収益
- 法人が行う事業(例:講座、イベント、物販)による事業収益
- その他の収益(補助金、雑収入など)
特に変更する必要はありません。
第39条 資産の構成【必須】
第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。
この条文では、法人の資産を「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」に区分することを定めています。
これは、会計処理や報告義務において非常に重要な考え方です。
条文の解説
法人の資産は、以下のようなものから構成されます
- 設立時に提出した財産目録に記載された資産
- 正会員・賛助会員などからの入会金や会費
- 一般の支援者や企業などからの寄附金や寄附物品
- 預貯金や不動産などの保有資産から生じる利息・賃料等の収益
- 法人が行う事業(例:講座、イベント、物販)による事業収益
- その他の収益(補助金、雑収入など)
特に変更する必要はありません。
ただし、その他事業を行わない場合は、以下のように記載します
第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
第40条 資産の管理【必須】
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
この条文では、法人の資産管理の責任者と、その方法の決定手続きについて定めています。
資産の適正な管理と、ガバナンスの確保を目的とした基本ルールです。
条文の解説
法人の資産は、理事長が一元的に管理する責任を持ちます
特に変更する必要はありません。
第41条 資産の構成【必須】
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
この条文では、NPO法人の会計処理は「特定非営利活動促進法第27条」に定められた原則に従うことを明記しています。
条文の解説
NPO法人の会計は、NPO法第27条で定められた「3つの原則」に従う必要があります
- 正規簿記の原則:適切に記帳すること
- 真実性、明瞭性の原則:うそを書かずに、わかりやすく書くこと
- 継続性の原則:会計のルールを毎年統一すること
特に変更する必要はありません。
第42条 会計の区分
第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。
この条文では、法人の会計を「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」に分けて処理することを定めています。
これは、NPO法人の運営において必須の会計ルールです。
条文の解説
特定非営利活動に係る会計(本来事業)と、その他の事業に関する会計(収益事業など)は、それぞれ明確に区分して処理する必要があります
特に変更する必要はありません
ただし、その他の事業を行わない場合は以下のように記載します
第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。
第43条 事業計画及び予算
第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
この条文では、事業計画とそれに伴う予算の作成と決定の流れを定めています。
法人が計画的かつ適正に活動・資金運用を行うための基本ルールです。
条文の解説
毎年度の事業計画と活動予算は、理事長が案を作成し、総会の議決(承認)を経て正式に決定されます
特に変更する必要はありません
第44条 暫定予算
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす
この条文では、新年度の予算が総会でまだ承認されていない場合に、暫定的に前年度予算を基に執行できる仕組みについて定めています。
予算未成立時の混乱を防ぎ、法人活動を止めないためのルールです。
条文の解説
総会で新年度の予算がまだ成立していない場合、理事長は理事会の議決を経て、前年度の予算に準じた執行を行うことができます
あとから正式な予算が成立した際には、暫定で支出した費用は「当該年度の正式な予算」に含まれる扱い(みなされる)になります
特に変更する必要はありません
第45条 予算の追加及び更正
第45条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
この条文では、予算が成立した後でも、やむを得ない事情が生じた場合には、総会の議決により予算を変更できることを定めています。
予算の柔軟な見直しを可能にし、実態に即した運営を行うための仕組みです。
条文の解説
予算成立後でも、状況の変化(例:助成金の追加採択、物価高騰、事業の中止や新設など)があれば、「追加予算」または「予算の更正(修正)」が可能です
ただし、勝手に変更せず、必ず総会の議決を経る必要がある点がポイントです
特に変更する必要はありません
第46条 事業報告及び決算
第46条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
この条文では、決算書類の作成から承認までの手順と、剰余金の取扱いについて定めています。
NPO法人の財務報告の信頼性と透明性を担保するための基本ルールです。
条文の解説
決算書類の一式(※以下の4点セット)は、理事長が作成し、監事の監査を経て、総会で承認される必要があります
- 事業報告書(何をやったか)
- 活動計算書(いくら使って・得たか)
- 貸借対照表(資産と負債のバランス)
- 財産目録(保有財産のリスト)
剰余金(余ったお金)が発生した場合は、利益として分配することなく、次年度に繰り越す
特に変更する必要はありません
第47条 事業年度【必須】
第47条 この法人の事業年度は、毎年○月○日に始まり翌年○月○日に終わる。
この条文では、NPO法人の1事業年度の起算日と終了日を定めます。
会計・事業・報告のすべての基準となる大切な項目です。
条文の解説
NPO法人では、事業年度(=会計年度)を自由に定めることができます。
一般的には以下のようなパターンが多いです。
- 4月1日〜翌年3月31日(学校・行政と同じ年度)
- 1月1日〜12月31日(カレンダー通り)
- 7月1日〜翌年6月30日(助成金などとの整合性を重視する場合)
「毎年○月○日に始まり翌年○月○日」に具体的な月日を記載します
第48条 臨機の措置
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
この条文では、予算の範囲を超えて借入をしたり、新たな義務を負う・権利を放棄するような重要な判断を行う場合には、総会の議決が必要であることを定めています。
財務的なリスクを伴う行為に対して、会員の合意を得る仕組みです。
条文の解説
通常の活動に関する支出(予算内での支出)であれば、理事会の決定で執行できますが、以下のようなケースでは総会の議決が必要です:
- 予算外での借入れ(長期借入や多額の一時借入など)
- 大きな支出を伴う新たな義務の負担(例:設備投資、契約行為)
- 契約解除・放棄などによる権利の放棄(例:所有物件の無償譲渡など)
特に変更する必要はありません
第8章 定款の変更、解散及び合併
第49条 定款の変更【必須】
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
この条文では、定款を変更するための手続きと必要な条件を定めています。
特に、重要な変更には総会での特別多数決(4分の3以上)と、所轄庁の認証が必要です。
条文の解説
定款を変更するには、総会に出席した正会員の4分の3以上の同意が必要です
以下のような重要な変更をする場合は、所轄庁の「認証」も必要(NPO法第25条第3項に該当)
- 目的
- 名称
- 活動分野
- 主たる事務所の所在地
- 社員の資格の得喪に関する事項
- 役員に関する事項
- 会議に関する事項
- その他の事業に関する事項
- 解散に関する事項
- 定款の変更に関する事項
一方、それ以外の軽微な変更(例:文言修正、任意のルール調整など)は、「届出」だけでOKの場合もあります
特に変更する必要はありません
第50条 解散【必須】
第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
この条文では、NPO法人が解散する場合の理由(法定事由)と、それぞれに必要な手続きについて定めています。
団体の活動終了時に法的な混乱が起きないようにするための基本ルールです。
条文の解説
法人が解散する可能性のある事由は、以下の6つに分類されます:
- 総会の決議(任意解散)
- 目的事業の成功が不可能となったとき
- 正会員が1人もいなくなったとき(=法人の構成が成立しない)
- 他の法人との合併
- 裁判所による破産手続開始決定
- 所轄庁から設立認証を取り消されたとき
「1.総会の決議」による解散の場合には、正会員総数の4分の3以上の賛成が必要です(特別多数決)
「2.目的事業の成功が不可能となったとき」による解散は、所轄庁の認定が必要
特に変更する必要はありません
第51条 残余財産の帰属【必須】
第51条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。
この条文では、法人が解散した際に残った財産(残余財産)を誰に引き継ぐかを定めています。
NPO法人は非営利団体であるため、残余財産を個人や任意の団体に分配することはできず、法律に基づいて処理する必要があります。
条文の解説
NPO法人が解散する際、残っている財産(現金・物品・備品など)は、法第11条第3項に定められた公益的な団体等に譲渡しなければなりません
この条文では、合併・破産による解散を除く任意解散などの場合において、残余財産の譲渡先は総会で決議します
法第11条第3項に掲げられている「譲渡先の候補」は以下のような団体です
- 他のNPO法人
- 国または地方公共団体
- 公益社団法人・公益財団法人
- 学校法人
- 社会福祉法人
- 更生保護法人
特に変更する必要はありません
第52条 合併
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
この条文では、NPO法人が他の法人と合併するために必要な手続きを定めています。
合併は法人の存続に関わる重大な事項のため、特別な議決要件と行政手続きが必要です。
条文の解説
合併とは、法人が他の法人と統合し、一方が消滅し、一方が存続または新法人を設立する形態です
合併を行うには、以下の2つの条件を満たす必要があります
- 総会において、正会員総数の4分の3以上の議決(特別決議)
- 所轄庁の認証(法第30条に基づく)
特に変更する必要はありません
第9章 公告の方法
第53条 公告の方法【必須】
第53条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、○○○○に掲載して行う。
この条文では、法人の公告(情報公開)をどこに、どのように掲載するかについて定めています。
特に、貸借対照表の公告方法についてはNPO法の改正(法第28条の2)により明記が必要となっています。
条文の解説
一般的な公告(定款変更・合併・解散などの重要事項)は、「官報」に掲載して行うと定められています
一方で、貸借対照表の公告は、NPO法第28条の2により、以下のいずれかで掲載する必要があります。
- 官報
- 各都道府県において発行する○○新聞
- この法人のホームページ
- 内閣府NPO法人ポータルサイト(法人情報入力欄)
- この法人の主たる事務所の掲示板
「○○○○」には、各団体にあった掲載方法を記載してください
第10章 雑則
第54条 細則
第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
この条文では、定款に定めのない細かな運営ルール(細則)を、どのように定めるかについて規定しています。
法人運営に柔軟性を持たせるための仕組みです。
条文の解説
定款はあくまで“基本的なルール”にとどまり、実務運営の詳細(例:入会申込の様式、委員会の設置方法、文書管理など)は「細則」で補うことが一般的です
この条文により、理事会の議決を経て、理事長が細則を定められる体制が整えられます
特に変更する必要はありません
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 ○○ ○○
副理事長 ○○ ○○
理事 ○○ ○○
同 ○○ ○○
監事 ○○ ○○
同 ○○ ○○
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から○年○月○日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日から○年○月○日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)正会員入会金 ○○○円正会員会費 年額□□□円
(2)賛助会員入会金 △△△円
賛助会員会費 年額▽▽▽円
附則は、定款の本則とは別に「法人設立時の特例や具体情報」を定める条文群です。
主に、施行日・設立時の役員・初年度の事業年度や会費等、一時的または具体的に定めておくべき事項を明文化します。
条文の解説
1.施行日:この定款は、法人が法的に成立した日(=設立登記日)から効力を発することを明示。
2.設立当初の役員:誰がどの役職に就任するかを具体的に記載。定款の提出時には氏名をフルネームで記載します。
3.設立当初の役員の任期:第15条の「2年任期」にかかわらず、初回のみ柔軟な期間を設定可能(登記日から○年○月○日までなど)。
4.設立当初の事業計画・予算:通常は総会決議が必要ですが、設立総会の承認で済ませることを認めています(第43条の特例)。
5.初年度の事業年度:設立日から最初の年度末までを指定。通常は設立日〜3月31日や12月31日などが多いです。
6.当初の入会金・会費:正会員・賛助会員それぞれの初年度の金額を明記(第8条の特例)。設立総会で変更可。
まとめ|定款は“団体の未来”を支える大切な設計図
この記事では、NPO法人設立に必要な書類と定款の基本構成・書き方について解説しました。
要点をまとめると以下の通りです
- 定款はNPO法人の“ルールブック”であり、設立認証・登記に必須の書類
- 条文ごとに意味とポイントを押さえることが重要(例:第1条の名称、第3条の目的など)
- 各条文の実務的な背景やカスタマイズ方法も理解することで、より運営に合った定款が作成可能
定款作成では、「なぜそう書くのか」だけでなく、「どう書けば運営しやすくなるか」を意識することが重要なポイントとなります。
NPO法人の設立を検討されている方は、ぜひこのポイントを押さえて、実情にあった定款づくりにチャレンジしてみてください。
ご不明な点やご相談がある方は、こちらからお気軽にお問い合わせください。
NPO法人を自分で安心して設立できるよう、8つのステップに分けて以下の記事で解説しています。