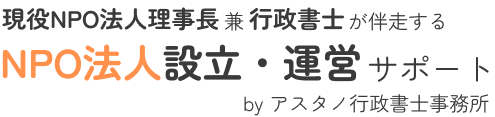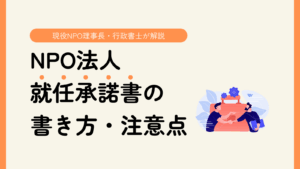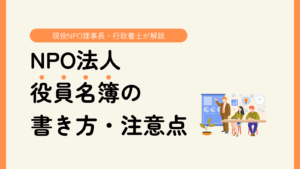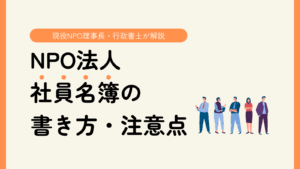NPO法人設立の流れ|初心者でもわかる6ステップ完全ガイド【現役NPO理事長が解説】
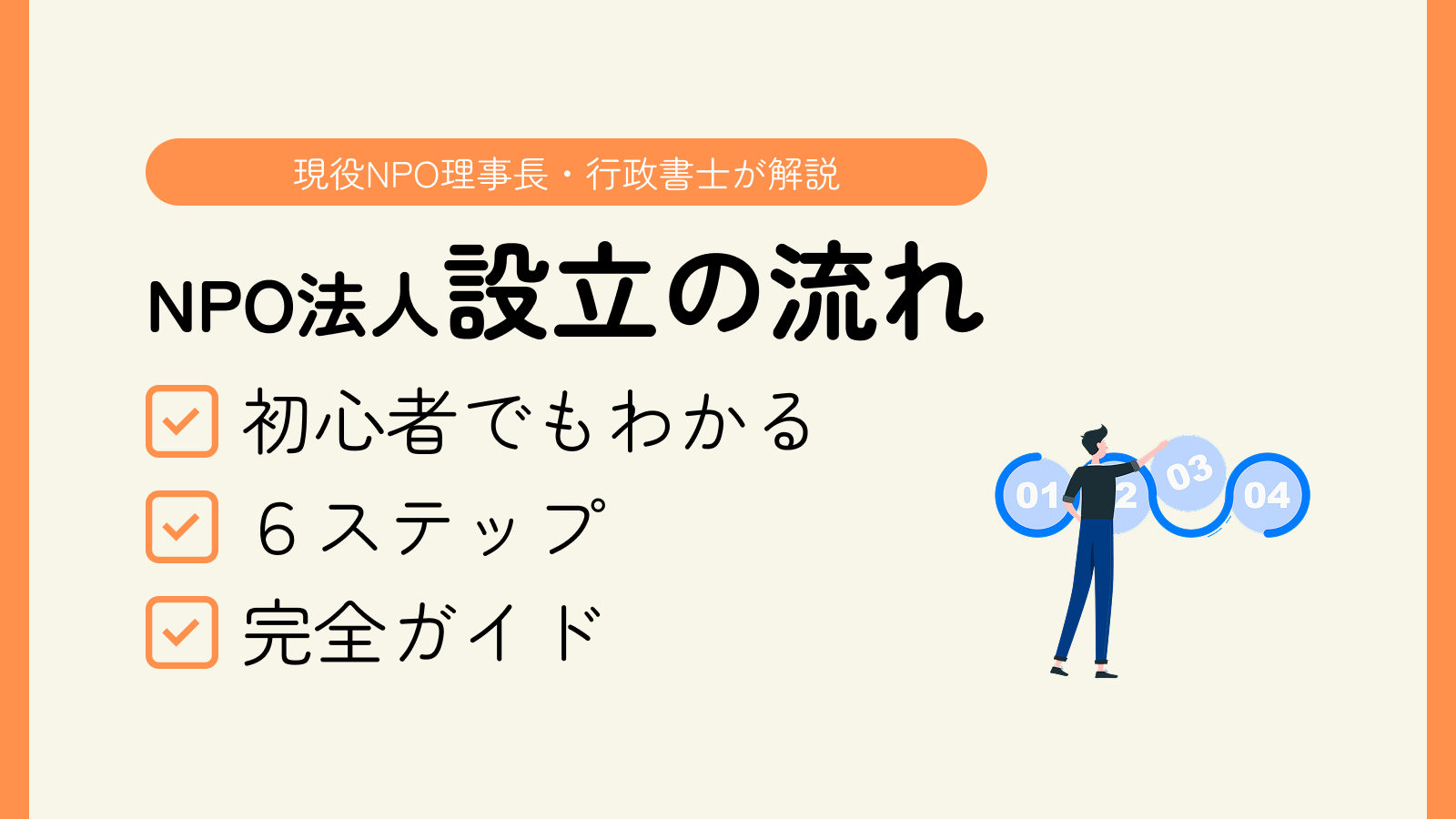
- NPO法人を作りたいけれど、何から始めればいいのかわからない
- 調べても情報がバラバラで、結局どう進めればいいのか迷ってしまう
- 手続きが複雑そうで、本当に自分ひとりでできるのか不安になる
実はNPO法人の設立には、定款の作成・社員10人の確保・設立総会・所轄庁への申請・法務局での登記など、いくつものステップがあります。
どれも聞き慣れない手続きばかりで、「結局、何からやればいいのか分からない…」と感じてしまう方が多いのが実情です。
この記事では、NPO法人の設立に必要な準備・手続きの流れを、全6ステップで順を追ってわかりやすく解説します。
この記事を読めば、NPO法人設立の全体像が明確になり、「何を・どの順番で・どこに届ければいいのか」が具体的にイメージできるようになります。
むずかしそうに見えても実は、ひとつずつ進めればきちんと形にできます。
このページを読み終えるころには、あなたの団体が一歩前に進むための地図が手に入っているはずです。
NPO法人設立する流れは?|6ステップで解説
NPO法人の設立は以下の6ステップで進みます。
- 基本事項の検討
- 設立に必要な書類の作成
- 設立総会の開催・議事録の作成
- 所轄庁への認証申請
- 法務局への登記申請
- 所轄庁や都道府県税事務所等への届出
1:基本事項の検討
まずは、設立するNPO法人を「どんな団体にしたいのか」を考えます。
活動の土台になる大切な部分なので、最初にしっかりイメージしておくことが大切です。
そのときに確認しておきたい項目は、以下のとおりです。
- 社員(=正会員)を10人以上集める
- 設立趣旨書の作成
- 定款の下書きを作成
- 組織のかたちをイメージ
- 役員案を考える
- 事業計画と予算案の作成
社員(=正会員)を10人以上集める
NPO法人を設立するには、社員(=正会員)を10人以上集めることが法的に必要です。
この条件を満たさないと、そもそもNPO法人設立の申請ができません。
- 正会員とは
NPO法人では、団体の大切なことを決める「総会」で投票できるメンバーを「正会員(=社員)」と呼びます。
お金を出す“株主”ではなく、「団体の活動や理念に共感して、一緒に考え、動かしてくれる仲間」とイメージするとわかりやすいです。
- 正会員とよく混同される人との違い
| 呼び名 | 内容 | 議決権(総会での投票権) |
|---|---|---|
| 正会員(社員) | 総会に参加できるメンバー | ある |
| 賛助会員 | 活動を応援するメンバー | なし |
| 理事・監事(役員) | 団体の運営を担う人。正会員から選ばれることが多い。 | ある |
| スタッフ(職員) | 団体からお金をもらって働く人。正会員でなくてもよい。 | なし |
社員に関する要件については、以下の記事で詳しく紹介しています。
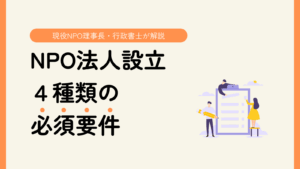
設立趣旨書の作成
NPO法人を設立するときに提出する書類のひとつに「設立趣旨書」があります。
この書類には「なぜNPO法人を立ち上げたいのか」その理由や想いを書く必要があります。
設立趣旨書には、主に次のような内容を記載します。
- 社会課題や現状
- 事業の概要
- 法人格が必要になった理由
- NPO法人を選んだ理由
- 申請に至るまでの経緯
設立趣旨書の書き方については、以下の記事で詳しく紹介しています。
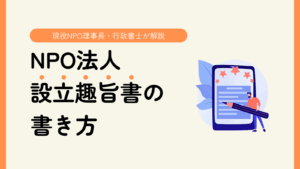
定款の下書きを作成
NPO法人を設立するときに提出する書類のひとつに「定款」があります。
この書類は、団体の目的や活動内容、役員の役割や総会の開催方法など、法人の基本ルールをまとめたものです。
定款には、主に次のような項目を記載します。
- 活動の目的や内容(どんなことをする団体なのか)
- 会員や役員の決め方(誰が参加できて、どんな役割があるのか)
- 総会や議事録のルール(いつ、どんなふうに話し合いをするのか)
- お金の使い方(どこに、どのように使うか)
- 合併や解散のルール(団体を終わらせるとき、どのようにするか)
定款の書き方については、以下の記事で詳しく紹介しています。
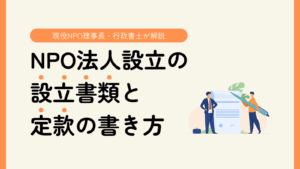
組織のかたちをイメージ
NPO法人を安定して運営するには、総会・理事会・事務局などの組織体制をあらかじめ考えておくことが大切です。
NPO法人は1人で運営するものではなく、みんなで意識決定をしながら進めていく必要があります。
そのために、無理のない仕組みをつくっておくことで、設立後にスムーズに活動できます。
各組織について
| 呼び名 | 内容 |
|---|---|
| 総会 | 正会員が参加し、団体の方針や活動内容を決める場。年1回以上は開催が必要。 |
| 理事会 | 理事が集まり、日常的な運営や活動の調整を行う場。 |
| 事務局 | 会計・書類の管理・問い合わせ対応など、日々の実務を担当する役割。 |
少人数の団体では、理事が事務局を兼ねるなど、役割を兼任するケースもあります。
大切なのは、「誰が何を担当するのか」を事前に明確にしておくことです。
役員案を考える
NPO法人を設立するには、理事3名以上・監事1名以上の役員を選ぶ必要があります。
理事・監事の役割
| 呼び名 | 内容 |
|---|---|
| 理事 | 団体を代表して、活動や運営を進める人 |
| 監事 | 団体の活動やお金の使い方をチェックする人 |
誰にどの役職をお願いするかは、団体の信頼性に直結する重要なポイントです。
役員を選ぶ際は、次の点を確認します。
- 役員が、理事3人以上、監事1人以上であること
- 役員が欠格事由に該当しないこと
- 役員が親族等の制限規定に違反しないこと
- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
役員の詳しい内容については、以下の記事で紹介しています。
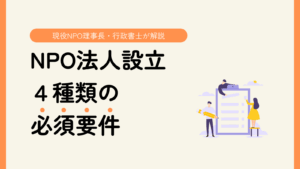
事業計画と予算案の作成
NPO法人を設立するには、2年間の事業計画と予算案を作成し、事業計画書と活動予算書として提出する必要があります。
事業計画書と活動予算書について
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業計画書 | 「誰に・何を・どのように」活動を行うかをまとめた書類 |
| 活動予算書 | どれくらい収入があり、どのようにお金を使うかをまとめた書類 |
これらがないと「この団体は本当に活動できるのか?」という疑問を持たれてしまいます。
完璧である必要はありませんが、無理のない現実的なプランを立てておくことが、設立後の安定した運営につながります。
事業計画書や活動予算書の書き方については、以下の記事で詳しく紹介しています。
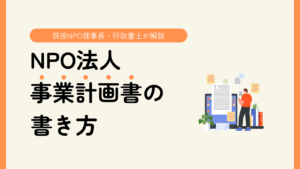
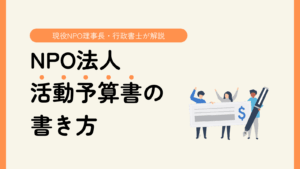
2:設立に必要な書類の作成
NPO法人を設立するには、いくつもの書類を準備して提出する必要があります。
書類に不備があると、受理されなかったり、差し戻されたりすることもあります。
提出する主な書類は、次のとおりです。
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 特定非営利活動法人設立認証申請書 | 各自治体のHPで公開されているものを使用 |
| 定款 | 団体の目的・事業内容・役員体制などをまとめた「基本ルール」 |
| 役員名簿 | 役員の氏名・住所(または居所)・報酬の有無を記載 |
| 役員の就任承諾書・誓約書(コピー) | 就任の同意と「欠格事由に該当しない」ことの誓約 |
| 役員の住民票 | マイナンバーの記載がないもの・発行から3か月以内 |
| 社員名簿 | 社員10名以上の名前・住所を記載 |
| 確認書 | NPO法の要件を満たしていることを確認する書類 |
| 設立趣旨書 | 団体を立ち上げた背景・目的などを記載 |
| 設立総会の議事録(コピー) | 設立総会での定款承認・役員選任などの決議内容を記録 |
| 事業計画書(初年度・翌年度) | 団体の活動内容について具体的に記載 |
| 活動予算書(初年度・翌年度) | 収入・支出の見込みを記載 |
提出部数や様式は自治体によって異なる場合があります。
そのため、資料を作成する前に、必ず所轄庁の案内を確認しておくことが大切です。
3:設立総会の開催・議事録の作成
NPO法人を設立するには、正会員による「設立総会」を開催し、その内容を記録した「議事録」を作成して提出する必要があります。
設立総会は、団体を法人として正式に立ち上げることを決める大切な場です。
そこでの決定事項をまとめた「議事録」には、次のような内容を記載する必要があります。
- NPO法人を設立する背景・目的について
- 役員について
- 定款について
- 事業計画書・活動予算書・財産目録について
- 設立代表者について
- 事務所の所在地について
設立総会の流れや議事録の書き方については、以下の記事で詳しく紹介しています。
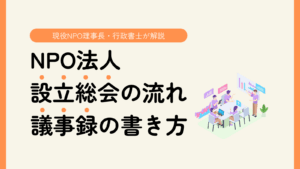
4:所轄庁への認証申請
設立総会が終わり、必要な書類がそろったら「所轄庁」へNPO法人設立の認証申請を行います。
所轄庁とは
所轄庁とは、団体の主な活動エリアを担当する都道府県または政令指定都市の窓口を指します。
(例:大阪市内で活動する団体なら「大阪市市民局」などが窓口になります)
所轄庁は内閣府NPOホームページから確認できます。
申請前に必ずチェックしておきましょう。
書類を提出してから認証が下りるまでには、約3~4ヶ月程度はかかります。
5:法務局への登記申請
所轄庁から「設立認証」を受けたら、2週間以内に法務局で「設立登記」の手続きを行います。
この登記が完了して、はじめて法人格が成立し、正式にNPO法人として活動できるようになります。
登記は、団体の主たる事務所を管轄する法務局で行います。
管轄する法務局は、法務局のHPで確認できますので、事前にチェックしておきましょう。
提出する主な書類は次のとおりです。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 特定非営利活動法人設立登記申請書 | 法務局のHPからダウンロード可 |
| 認証書(コピー) | 所轄庁から交付されたもの |
| 定款(コピー) | 所轄庁から交付されたもの |
| 印鑑届出書 | 法人印を登録するための書類 |
| 代表者の印鑑証明書 | 発行から3ヶ月以内のもの |
| 財産目録 | 設立時の財産状況を記載 |
| 就任承諾書 | 「理事長が代表する場合」と「理事全員が代表する」場合で異なる |
| 設立総会議事録(コピー) | 必要に応じて提出 |
登記が完了すると、以下の証明書類が取得可能になります
- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 法人印鑑証明書
これらは、口座開設や次のステップの所轄庁や税務署への設立届出で必要になるため、複数取得しておくと安心です。
登記の流れについては、以下の記事で詳しく紹介しています。
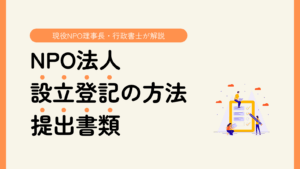
6:所轄庁や都道府県税事務所等への届出
登記が完了したら、所轄庁や都道府県税事務所など関係機関への届出が必要です。
それぞれの機関で提出する主な書類は以下のとおりです。
| 機関名 | 提出書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 所轄庁 | 設立登記完了届出書 | 各自治体のHPで公開されている様式を使用 |
| 登記事項証明書 | 法務局で発行 | |
| 設立時の財産目録 | ||
| 都道府県税事務所 | 法人設立等申告書 | |
| 市区町村 | 法人等設立申告書 |
必要な書類や様式は各自治体によって異なるため、事前に各機関のHPで確認しておきましょう。
所轄庁への提出方法|窓口・郵送・オンライン・代理、どれを選ぶ?
NPO法人を設立する際、所轄庁へ書類を提出する必要があります。
提出方法には、窓口での提出・郵送・オンライン申請・代理人による提出の4つがあります。
それぞれに特徴やメリット・注意点があるので、理解したうえで自分たちに合った方法を選びましょう。
迷った場合は「窓口での提出」がおすすめです。
その場で不備を指摘してもらえるため、初めてでも安心して進められます。
| 提出方法 | 特徴 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 窓口 | 所轄庁に直接提出 | 不備をその場で確認できる | 平日の日中に行く必要がある |
| 郵送 | 郵便で提出 | 時間の自由が利く | 書類不備による差し戻しのリスク |
| オンライン申請 | 電子申請 | 自宅から手続き可能 | 対応していない所轄庁が多い |
| 代理申請(専門家に依頼) | 行政書士に相談 | ミスの心配が少ない | 費用がかかる |
もし現時点で書類を何も作成していない場合は、行政書士に依頼するのもひとつの方法です。
費用はかかりますが、書類の不備を防ぎ、時間を節約できるため、安心して手続きを進めることができます。
行政書士に依頼するメリットや具体的な流れについては、以下の記事で詳しく紹介しています。
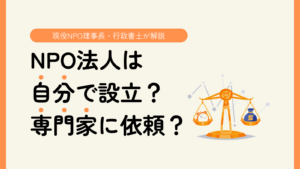
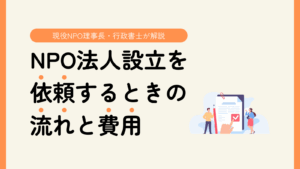
よくある質問
NPO法人設立に関する手続きについて、よくある質問を3つご紹介します。
- NPO法人を設立するのにどれくらい時間がかかる?
- 役員や社員に家族を含めても大丈夫?
- お金はどのくらいかかる?
Q:NPO法人を設立するのにどれくらい時間がかかる?
A. 一般的には約4~6ヶ月かかります。
いくつかのステップを踏む必要があり、特に所轄庁での認証手続きに時間がかかるためです。
具体的な流れと目安期間は次のとおりです。
| ステップ | 目安期間 |
|---|---|
| 準備〜書類作成 | 約1〜2ヶ月 |
| 所轄庁への申請〜認証 | 約3~4ヶ月 |
| 登記・各種届出などの手続き | 約1〜2週間 |
Q:社員や役員に家族を含めても大丈夫?
A. 社員に関しては大丈夫、役員に関しては一定の条件を守れば、問題ありません。
NPO法では、役員について「親族などが全体の3分の1以下であること」が求められています。
- 理事3人中2人が親族→NG
- 理事6人中2人が親族→OK
一方で、社員についてはこのような制限はありません。
NPO法人を設立するには他にも要件があり、詳しくは以下の記事で紹介しています。
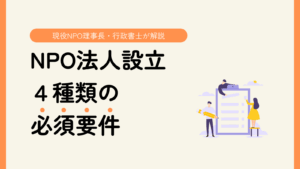
Q:お金はどのくらいかかる?
A:NPO法人の設立は、自分で手続きを行う場合、約1万円程度で始められます。
一般社団法人など他の法人に比べて、費用を大きく抑えられるのが特徴です。
| 費用項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 設立認証申請 | 0円(収入印紙なども不要) |
| 登記(登録免許税) | 0円(非課税) |
| 法人印鑑作成 | 約3,000〜5,000円程度 |
| 郵送・コピー代などの実費 | 約1,000〜3,000円程度 |
行政書士などの専門家に依頼する場合は、15~25万円程度かかることもあります。
自分で設立するか、専門家に依頼するかの判断ポイントについては、以下の記事で詳しく紹介しています。
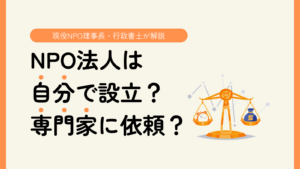
まとめ|NPO法人設立は書類の正確さと順番通りにすすめること
この記事では、NPO法人の設立の流れや提出方法についてわかりやすく解説しました。
要点をまとめると以下の通りです。
- NPO法人の設立は、6つのステップに分けて順番に進めれば大丈夫
- 書類の提出方法で迷ったら、窓口での提出がおすすめ
- 準備ができていない場合は、行政書士に依頼するのもひとつの方法
NPO法人の設立では、書類の正確さと順番通りに進めることが重要なポイントとなります。
ぜひこの記事でご紹介したポイントを押さえて、無理なく、確実にNPO法人設立を進めてみてください。
さらに詳しく知りたい方はこちらの記事もどうぞ。
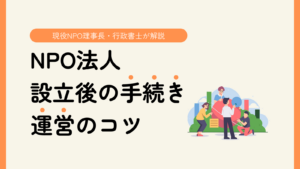
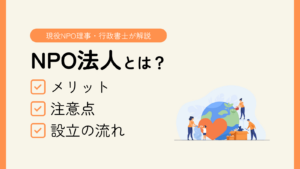
- ここまで読んだけど、やっぱり自分だけでできるか不安…
- 自分の団体の場合はどう進めるべきか、わからない…
- 手続きで失敗したり、差し戻されたりしないか心配…
そんな方のために、現役NPO理事長でもある行政書士が、あなたの状況にあわせて個別にアドバイスいたします。
- 電話・LINE・Zoomで柔軟にご対応!
- 初回の対面・Zoomによる面談は無料!
- 設立だけでなく、その後の運営も含めてご相談可!